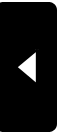2020年07月11日
2020年07月11日
キヨスミウツボ
7月3日
<キヨスミウツボ>
キヨスミウツボ(清澄靫) ハマウツボ科。カシ類、アジサイ類の根に寄生する寄生植物。花名の由来は、千葉県の清澄山で発見され、花の形が弓矢を入れる靫(うつぼ)に似ることから。
ここのものは、ツルアジサイに寄生か、その根元に生育しています。






<ツルアジサイ>

<ギンリョウソウ(ピンク)>



<ギンリョウソウ(終盤)>

<キヨスミウツボ>
キヨスミウツボ(清澄靫) ハマウツボ科。カシ類、アジサイ類の根に寄生する寄生植物。花名の由来は、千葉県の清澄山で発見され、花の形が弓矢を入れる靫(うつぼ)に似ることから。
ここのものは、ツルアジサイに寄生か、その根元に生育しています。

<ツルアジサイ>
<ギンリョウソウ(ピンク)>
<ギンリョウソウ(終盤)>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2020年07月10日
葦毛湿原
7月9日
この雨で、湿原に日参しています。次の、タンザワウマノスズクサが3日連続で弾けました。
<タンザワウマノスズクサ>


これは、あと少しかな?

<トモエソウ>
今年は株数が少ないが、未だ、これからなのかも知りません。


<ヒナノシャクジョウ>





<ニュース>
私の師匠・葦毛湿原のエキスパートがブログ再開しましたので宜しくお願いします。最近は粘菌に嵌っているようです。私の”お気に入り”のTOPにある”野の花 山の花”です。
この雨で、湿原に日参しています。次の、タンザワウマノスズクサが3日連続で弾けました。
<タンザワウマノスズクサ>
これは、あと少しかな?
<トモエソウ>
今年は株数が少ないが、未だ、これからなのかも知りません。
<ヒナノシャクジョウ>
<ニュース>
私の師匠・葦毛湿原のエキスパートがブログ再開しましたので宜しくお願いします。最近は粘菌に嵌っているようです。私の”お気に入り”のTOPにある”野の花 山の花”です。
Posted by 吾亦紅 at
04:00
2020年07月10日
2020年07月09日
葦毛湿原
7月8日
<タンザワウマノスズクサ>
弾けた種。2個目です。

<ノカンゾウ>
これから、近くでも見られるようになります。

<ヒメヤブラン>

<ホンゴウソウ>
晴れると、もう少し、良い画像が期待できますが。





<ヤブデマリ>

<タンザワウマノスズクサ>
弾けた種。2個目です。
<ノカンゾウ>
これから、近くでも見られるようになります。
<ヒメヤブラン>
<ホンゴウソウ>
晴れると、もう少し、良い画像が期待できますが。


<ヤブデマリ>
Posted by 吾亦紅 at
11:49
2020年07月09日
アラカルト
7月3日
<カラスウリの花>

<トチバニンジン>

<ヤブレガサ>

<ノハナショウブ>

<オカトラノオ>

<バイケイソウ>

<キツリフネ>

<キバナノヤマオダマキ>


<カラスウリの花>
<トチバニンジン>
<ヤブレガサ>

<ノハナショウブ>
<オカトラノオ>
<バイケイソウ>
<キツリフネ>
<キバナノヤマオダマキ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2020年07月08日
湿原(葦毛)
7月7日
毎日、いやなお天気で、悶々とする今日この頃。午後、少し雨が上がったので、湿原散歩。こんな日でも、会長や、はらっちさんに出会いました。トモエソウが咲いたというので、期待しましたが、1輪ほどでしたが、期待していなかったウマノスズクサが弾けていました!ノカンゾウは今日も見られず。
<トモエソウ>
未だ早いですが、雨で倒れてしまわないか心配です!


<ウマノスズクサ>
天気の所為か、今一。過去の経験から、午前中の方がいい気がします。

<シュロソウ>
笹の中に埋もれています。

<トンボソウ>
湿原内。まだまだです。

<ヌマトラノオ>

<ヤブデマリ>

まだまだ、この天気は続きそうですが、私の住み地域は、埋立地で、海抜1m、豊川が氾濫すればお仕舞いという地域、でも幸い、今まで、大きな水害に合っていません。九州や岐阜県で被害に会われた方にお悔やみ申し上げます。
毎日、いやなお天気で、悶々とする今日この頃。午後、少し雨が上がったので、湿原散歩。こんな日でも、会長や、はらっちさんに出会いました。トモエソウが咲いたというので、期待しましたが、1輪ほどでしたが、期待していなかったウマノスズクサが弾けていました!ノカンゾウは今日も見られず。
<トモエソウ>
未だ早いですが、雨で倒れてしまわないか心配です!

<ウマノスズクサ>
天気の所為か、今一。過去の経験から、午前中の方がいい気がします。
<シュロソウ>
笹の中に埋もれています。
<トンボソウ>
湿原内。まだまだです。
<ヌマトラノオ>

<ヤブデマリ>
まだまだ、この天気は続きそうですが、私の住み地域は、埋立地で、海抜1m、豊川が氾濫すればお仕舞いという地域、でも幸い、今まで、大きな水害に合っていません。九州や岐阜県で被害に会われた方にお悔やみ申し上げます。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2020年07月07日
葦毛湿原のこれから
7月5日
ノカンゾウも開花したようですが、1日花で、この日は花は見られませんでした。サギソウをはじめ、これから7月中旬から、月末にかけ、楽しみかと思います。
<ミミカキグサ>


<ムラサキミミカキグサ>

ヒメミミカキグサも、これから楽しみです。一説によると、昨年、97株の話もありますが。。。。?
<ヒナノシャクジョウ>

<ホンゴウソウ>

<コオニユリ>

<トモエソウ>

<ミズオトギリ>

ノカンゾウも開花したようですが、1日花で、この日は花は見られませんでした。サギソウをはじめ、これから7月中旬から、月末にかけ、楽しみかと思います。
<ミミカキグサ>
<ムラサキミミカキグサ>
ヒメミミカキグサも、これから楽しみです。一説によると、昨年、97株の話もありますが。。。。?
<ヒナノシャクジョウ>
<ホンゴウソウ>
<コオニユリ>
<トモエソウ>
<ミズオトギリ>
Posted by 吾亦紅 at
04:00
2020年07月07日
2020年07月06日
葦毛湿原の今
7月5日
<オオバトンボソウ>



こちらは、少し感じが違う気がします。



<コケオトギリソウ>

<ヌマトラノオ>

<ヒメヤブラン>

<ヤブデマリ>



<オオバトンボソウ>
こちらは、少し感じが違う気がします。
<コケオトギリソウ>
<ヌマトラノオ>
<ヒメヤブラン>
<ヤブデマリ>
Posted by 吾亦紅 at
09:15
2020年07月06日
ヤワタソウ
6月28日
八幡草 ユキノシタ科 ヤワタソウ属。
薄いクリーム色というか、淡黄白色というか、そんな色の花です。花弁は5個で、別名をオトメソウと言いますが、花だけ見ていると納得できる可愛さです。葉に比べて小さいと言うべきか、花に比べて葉が大きいと言うべきか。根生葉は本当に大きいのです。

大きくなる葉は、根生葉。茎葉はさほど大きくはなく、数個が互生します。



雄しべは上からだと、葯が三角っぽく見えます。

八幡草 ユキノシタ科 ヤワタソウ属。
薄いクリーム色というか、淡黄白色というか、そんな色の花です。花弁は5個で、別名をオトメソウと言いますが、花だけ見ていると納得できる可愛さです。葉に比べて小さいと言うべきか、花に比べて葉が大きいと言うべきか。根生葉は本当に大きいのです。
大きくなる葉は、根生葉。茎葉はさほど大きくはなく、数個が互生します。
雄しべは上からだと、葯が三角っぽく見えます。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2020年07月05日
アラカルト
6月28日。
<ジガバチソウ>

<ヨウシュウヤマゴボウ>

<キカラスウリ>
やはり、普通のカラスウリとは花が違うのが分かります。


因みに、2019年9月13日のカラスウリです。

<カギカズラ>


<マタタビ>
葉の白が中々出せません。



<イワツツジ>

<キノコ>

<ジガバチソウ>
<ヨウシュウヤマゴボウ>
<キカラスウリ>
やはり、普通のカラスウリとは花が違うのが分かります。
因みに、2019年9月13日のカラスウリです。
<カギカズラ>

<マタタビ>
葉の白が中々出せません。
<イワツツジ>
<キノコ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2020年07月04日
キバナアキギリ
6月28日
<キバアキギリ>
キバナアキギリは、花の形が桐の花に似て秋に紫色の花が咲くアキギリに対し、花が黄色なのでキバナアキギリの名がある。 属名ともなっているアキギリは中部から関西の山の中に多く、キバナアキギリは全国どこでも山裾で見られる花で、春の若菜は和え物やおひたしとして食べられたようである。キバナアキギリやアキノタムラソウは日本のサルビアである。

ども、ここの花は白っぽい!



写真の紫色の長い糸状のものが雌しべ、その根本に雄しべが有る。

葉が特徴的ですね! 葉の形が琴の弦を支える琴柱(ことじ)に似ているのでコトジソウとも呼ばれる。

<ヤワタソウ>


<キバアキギリ>
キバナアキギリは、花の形が桐の花に似て秋に紫色の花が咲くアキギリに対し、花が黄色なのでキバナアキギリの名がある。 属名ともなっているアキギリは中部から関西の山の中に多く、キバナアキギリは全国どこでも山裾で見られる花で、春の若菜は和え物やおひたしとして食べられたようである。キバナアキギリやアキノタムラソウは日本のサルビアである。

ども、ここの花は白っぽい!
写真の紫色の長い糸状のものが雌しべ、その根本に雄しべが有る。
葉が特徴的ですね! 葉の形が琴の弦を支える琴柱(ことじ)に似ているのでコトジソウとも呼ばれる。
<ヤワタソウ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2020年07月03日
2020年07月02日
葦毛湿原
7月1日
<ホンゴウソウ>



<ヒナノシャクジョウ>
あと、1週間か!

<オオバトンボソウ>
いいものは盗掘されていました。

<ウマノスズクサ>
残り6個。




この子は体長が5mmくらいで、目を離すと枯葉と同化して見つかりません。何ガエル?

<アベマキ>
一見、遠目ではカギカズラかと思いきや、蔓ではなく、木で、葉もコナラのよう。仲間に聞くと、アベマキだそうです。調べると、” 別名はコルククヌギ。山地に生える雌雄同株の落葉高木。樹皮は押すと弾力があり、コルク材や薪炭材としても利用されました。現在では椎茸の原木として利用されることが多いようです。葉うらに毛を密生し灰褐色であることからクヌギとは区別できます。 春に花が咲き、その翌年の秋に堅果(どんぐり)が実ります。”と、ありました。

<ホンゴウソウ>

<ヒナノシャクジョウ>
あと、1週間か!
<オオバトンボソウ>
いいものは盗掘されていました。
<ウマノスズクサ>
残り6個。
この子は体長が5mmくらいで、目を離すと枯葉と同化して見つかりません。何ガエル?
<アベマキ>
一見、遠目ではカギカズラかと思いきや、蔓ではなく、木で、葉もコナラのよう。仲間に聞くと、アベマキだそうです。調べると、” 別名はコルククヌギ。山地に生える雌雄同株の落葉高木。樹皮は押すと弾力があり、コルク材や薪炭材としても利用されました。現在では椎茸の原木として利用されることが多いようです。葉うらに毛を密生し灰褐色であることからクヌギとは区別できます。 春に花が咲き、その翌年の秋に堅果(どんぐり)が実ります。”と、ありました。
Posted by 吾亦紅 at
04:00