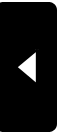2017年09月16日
ヤマジノホトトギスほか
9月10日
<ヤマジノホトトギス>



<サワギキョウ>

<ツリフネソウ>

<ヤマトリカブト>

<ナンバンハコベ>

<ヤブマメ>

<?ハグマ>


<ヤマジノホトトギス>
<サワギキョウ>
<ツリフネソウ>
<ヤマトリカブト>
<ナンバンハコベ>
<ヤブマメ>
<?ハグマ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月15日
2017年09月14日
シャクジョウソウ
9月10日
<シャクジョウソウ>
アキノギンリョウソウを探してたら、出会えました。初めての出会いに感激!シャクジョウソウ (錫杖草) は、イチヤクソウ科シャクジョウソウ属の多年草です。 褐色にした ギンリョウソウ(銀竜草) と言った感じの植物で、森林や丘陵地の小道など、陽がささない木陰に、キノコと見間違えそうな外観でヌメヌメと生える腐生植物(菌根植物)です。
花冠は鐘形をした総状花序で、茎の先端部に複数個が下向きに付き、 その姿が僧侶や修験者が手に持つ錫杖(シャクジョウ。環の付いた杖)に似ていることから、 シャクジョウソウ(錫杖草)という名付けられました。咲き進むにつれ、 花は徐々に上向きとなり、実を付ける時になると真っ直ぐになります。果実は立ち上がるようにして付きます。
植物は、通常、葉緑素を持ち、それを使って自分自身で栄養分を作り出し生活していますが、 シャクジョウソウのような腐生植物は、葉緑素を持たないため自分で栄養分を作り出せません。 そこで、根の表面近くにある菌根が分解する枯れ葉の栄養分の残りを吸収して生活しています。また、全草に葉緑素が無いので、薄茶色をしています。


<アキノギンリョウソウ>





<ウメバチソウ蕾>

<センボンヤリ蕾>

<シャクジョウソウ>
アキノギンリョウソウを探してたら、出会えました。初めての出会いに感激!シャクジョウソウ (錫杖草) は、イチヤクソウ科シャクジョウソウ属の多年草です。 褐色にした ギンリョウソウ(銀竜草) と言った感じの植物で、森林や丘陵地の小道など、陽がささない木陰に、キノコと見間違えそうな外観でヌメヌメと生える腐生植物(菌根植物)です。
花冠は鐘形をした総状花序で、茎の先端部に複数個が下向きに付き、 その姿が僧侶や修験者が手に持つ錫杖(シャクジョウ。環の付いた杖)に似ていることから、 シャクジョウソウ(錫杖草)という名付けられました。咲き進むにつれ、 花は徐々に上向きとなり、実を付ける時になると真っ直ぐになります。果実は立ち上がるようにして付きます。
植物は、通常、葉緑素を持ち、それを使って自分自身で栄養分を作り出し生活していますが、 シャクジョウソウのような腐生植物は、葉緑素を持たないため自分で栄養分を作り出せません。 そこで、根の表面近くにある菌根が分解する枯れ葉の栄養分の残りを吸収して生活しています。また、全草に葉緑素が無いので、薄茶色をしています。
<アキノギンリョウソウ>
<ウメバチソウ蕾>
<センボンヤリ蕾>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月13日
2017年09月12日
ツルニンジン他
9月10日
<ツルニンジン>
草刈に合い、足元に残って咲いていました。


こちらは、蔓が延びて、蕾も4個以上付いていました。

<ヤマトリカブト>



<ママコノシリヌグイ>

<ゲンノショウコ>



<ツルニンジン>
草刈に合い、足元に残って咲いていました。
こちらは、蔓が延びて、蕾も4個以上付いていました。
<ヤマトリカブト>
<ママコノシリヌグイ>
<ゲンノショウコ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月11日
ア・ラ・カ・ル・ト
9月4日
<ワレモコウ>
私のハンドルネームの花ですが、風にそよぎ、写真撮影が難しいですが、このようにアップで撮って、開花した花を観察するのが楽しみです。


<ミゾカクシ>

<ミズギボウシ白>

<ツリガネニンジン>

<ツユクサ>

<オオニシキソウ>

<オトギリソウ>

<ワレモコウ>
私のハンドルネームの花ですが、風にそよぎ、写真撮影が難しいですが、このようにアップで撮って、開花した花を観察するのが楽しみです。
<ミゾカクシ>
<ミズギボウシ白>
<ツリガネニンジン>
<ツユクサ>
<オオニシキソウ>
<オトギリソウ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月10日
水草
9月4日
<コナギ>


<オモダカ?>
この花に似たものは、アギナシ、ウリカワ、クワイなどがあります。葉の細さが違うとも言われますが、個体差もあり、実際区別がつきません。 一方、長年に渡って本種をはじめとする水田雑草の除去に「水稲用一発処理除草剤」という利便性及びコストパフォーマンスに優れた除草剤を使用して来た水田ではアゼナ類やホタルイ類とともにオモダカも除草剤に抵抗性を有する「スーパー雑草化」したものが見られ始めたという。 スーパー雑草化したオモダカの特徴は短時間で驚異的な繁殖を行い、これに取り付かれた水田では米の収穫量が20~30%も減少する。既存の除草剤も効かないために人手で除去することになるが、稲作農家の高齢化があり大きな問題となっている。

<ミズオオバコ>
大分生きの長い花です。この時期になると、ピンクになり、かわいさが増します。

お百姓さんには、邪魔者のようで、84歳のお爺さんが、田んぼの草取り中、取り除いていました。それを見た、山歩きの叔父さんが、2株頂く了解を得ていました。

この虫が時々、服に付いており、取るのに苦労します。

<メハジキ>
こちらは別の場所です。


<コナギ>
<オモダカ?>
この花に似たものは、アギナシ、ウリカワ、クワイなどがあります。葉の細さが違うとも言われますが、個体差もあり、実際区別がつきません。 一方、長年に渡って本種をはじめとする水田雑草の除去に「水稲用一発処理除草剤」という利便性及びコストパフォーマンスに優れた除草剤を使用して来た水田ではアゼナ類やホタルイ類とともにオモダカも除草剤に抵抗性を有する「スーパー雑草化」したものが見られ始めたという。 スーパー雑草化したオモダカの特徴は短時間で驚異的な繁殖を行い、これに取り付かれた水田では米の収穫量が20~30%も減少する。既存の除草剤も効かないために人手で除去することになるが、稲作農家の高齢化があり大きな問題となっている。
<ミズオオバコ>
大分生きの長い花です。この時期になると、ピンクになり、かわいさが増します。
お百姓さんには、邪魔者のようで、84歳のお爺さんが、田んぼの草取り中、取り除いていました。それを見た、山歩きの叔父さんが、2株頂く了解を得ていました。
この虫が時々、服に付いており、取るのに苦労します。
<メハジキ>
こちらは別の場所です。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月09日
2017年09月09日
ミシマサイコほか
9月8日
<ミシマサイコ>


<スズサイコ>
6月24日に、ここの違う場所で、夕方咲き始めたのを、撮影しました。2ヶ月以上前です。それなのに、今日は午前10時頃でしたが、まだ咲いていました。こんなに、息の長いものでしょうか?

<ナンバンギセル>

<ヤマジノホトトギス>


<ミシマサイコ>
<スズサイコ>
6月24日に、ここの違う場所で、夕方咲き始めたのを、撮影しました。2ヶ月以上前です。それなのに、今日は午前10時頃でしたが、まだ咲いていました。こんなに、息の長いものでしょうか?
<ナンバンギセル>
<ヤマジノホトトギス>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月08日
アラカルト
9月5日
<ヒガンバナ>
キツネノオオカミソリとは違うような?


<マツムシソウ>

<オミナエシ>

<ガガイモ>

<ミズギボウシ>

<コウヤボウキ>

<コケオトギリ>

<タムラソウ>

<ヒガンバナ>
キツネノオオカミソリとは違うような?
<マツムシソウ>
<オミナエシ>
<ガガイモ>
<ミズギボウシ>
<コウヤボウキ>
<コケオトギリ>

<タムラソウ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月07日
ア・ラ・カ・ル・ト
9月6日
<アオツヅラフジ>

<アケビ>

<ビナンカズラ雌花>

<ホシザキミミカキグサ>

<シラタマホシクサ>

ツルボに似ていますが?


<アオツヅラフジ>
<アケビ>
<ビナンカズラ雌花>
<ホシザキミミカキグサ>
<シラタマホシクサ>
ツルボに似ていますが?
Posted by 吾亦紅 at
05:00
2017年09月07日
ミヤマウズラ
9月3日
ラン科、シュスラン属の多年草。和名は「深山鶉」で、葉の模様をウズラの羽(卵といわれることもある)の模様に見立ててつけられているが、名前ほど深い山に生育しているわけではなく、低山帯、丘陵地でもよく見られる。










ラン科、シュスラン属の多年草。和名は「深山鶉」で、葉の模様をウズラの羽(卵といわれることもある)の模様に見立ててつけられているが、名前ほど深い山に生育しているわけではなく、低山帯、丘陵地でもよく見られる。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月06日
富岡地区(2)
8月30日
<オオヒキヨモギ>

<コウヤボウキ>

<オミナエシ>

<アキカラマツ>

<コガンピ>

<キキョウ>



<アギナシ>
花はありませんでしたが、葉が特徴的。

<オオヒキヨモギ>
<コウヤボウキ>
<オミナエシ>
<アキカラマツ>
<コガンピ>
<キキョウ>
<アギナシ>
花はありませんでしたが、葉が特徴的。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月05日
ナンバンギセル
8月29日
<ナンバンギセル>



<シュウカイドウ>[秋海棠]
淡いピンクの長い花が下向きに咲く。 雄と雌が同じ株で、茎の上に雄花があり下部に雌花がつく。いわゆるベゴニアの一種である。 和名の由来は、花の色がバラ科の海棠(カイドウ)に似ていて、秋に開花することからきている。原産地は中国、 日本へは江戸時代の初期に観賞用として渡来した。


<フシグロセンノウ>

<モミジガサ>

<サネカズラ>
雌花

雄花


<ナンバンギセル>
<シュウカイドウ>[秋海棠]
淡いピンクの長い花が下向きに咲く。 雄と雌が同じ株で、茎の上に雄花があり下部に雌花がつく。いわゆるベゴニアの一種である。 和名の由来は、花の色がバラ科の海棠(カイドウ)に似ていて、秋に開花することからきている。原産地は中国、 日本へは江戸時代の初期に観賞用として渡来した。
<フシグロセンノウ>
<モミジガサ>
<サネカズラ>
雌花
雄花
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月04日
ミズトラノオほか
9月3日
<ミズトラノオ>

<ルツボ>

<キンミズヒキ>

<ミズヒキ>

白っぽいヤブラン




愛大ダンス部が合宿して、豊橋祭りに向けて練習中。

昼食に立ち寄ったお店のツルウメモドキ。毎年、室内、全体に、豪華に飾ってあります。

<ミズトラノオ>
<ルツボ>
<キンミズヒキ>
<ミズヒキ>
白っぽいヤブラン
愛大ダンス部が合宿して、豊橋祭りに向けて練習中。
昼食に立ち寄ったお店のツルウメモドキ。毎年、室内、全体に、豪華に飾ってあります。
Posted by 吾亦紅 at
05:00
2017年09月04日
富岡地区(1)
8月30日
<シュロソウ>



<ミカワマツムシソウ>


<ミズオオバコ>
色がピンクになってきました。

<ルツボ>
画像:ルツボsk2k_1.JPG>
<ワレモコウ>


<ガガイモ>



<ママコノシリヌグイ>


シュロソウやワレモコウは葦毛湿原でもそろそろ、見られるのでは?
因みに、弓張山地のミヤマウズラも開花したようです。
<シュロソウ>
<ミカワマツムシソウ>
<ミズオオバコ>
色がピンクになってきました。
<ルツボ>
画像:ルツボsk2k_1.JPG>
<ワレモコウ>
<ガガイモ>
<ママコノシリヌグイ>
シュロソウやワレモコウは葦毛湿原でもそろそろ、見られるのでは?
因みに、弓張山地のミヤマウズラも開花したようです。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月03日
ミヤマウズラ
9月2日。弓張山地のミヤマウズラがいつもの場所周辺で、2株が咲き始めました。
<ミヤマウズラ>






<シュロソウ>

<ヌマダイコン>

<アレチノヌスビトハギ>

<ツルアリドオシ>

<変なカマキリ>

<ミヤマウズラ>
<シュロソウ>
<ヌマダイコン>
<アレチノヌスビトハギ>
<ツルアリドオシ>
<変なカマキリ>
Posted by 吾亦紅 at
05:00
2017年09月03日
北設楽方面(5)
8月23日。
<シデシャジン>
四手沙参。 和名の由来は神社のしめ縄や玉串などにつける白い紙(四手)のように花が細く裂けることから。またシャジン(沙参)とは漢方の咳止めからきた名前で、植物では ツリガネニンジン の別名に当たる。


<ヌスビトハギ?>

<ハグロソウ>

<ホタルブクロ>

?


<トチバニンジン>


?


北設楽方面は、これが最後です。
<シデシャジン>
四手沙参。 和名の由来は神社のしめ縄や玉串などにつける白い紙(四手)のように花が細く裂けることから。またシャジン(沙参)とは漢方の咳止めからきた名前で、植物では ツリガネニンジン の別名に当たる。

<ヌスビトハギ?>
<ハグロソウ>
<ホタルブクロ>
?
<トチバニンジン>
?
北設楽方面は、これが最後です。
Posted by 吾亦紅 at
00:00
2017年09月02日
マネキグサ
8月29日
<マネキグサ> シソ科マネキグサ属。
全国では絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。愛知県ではランク外。和名の由来は花冠が手招きしているように見えるということらしい。オドリコソウ属 に分類されていることもある。




<ツルリンドウ>

<シロバナイナモリソウ>

<ゲンノショウコ>

<クサアジサイ>

<マネキグサ> シソ科マネキグサ属。
全国では絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。愛知県ではランク外。和名の由来は花冠が手招きしているように見えるということらしい。オドリコソウ属 に分類されていることもある。
<ツルリンドウ>
<シロバナイナモリソウ>
<ゲンノショウコ>
<クサアジサイ>
Posted by 吾亦紅 at
00:00